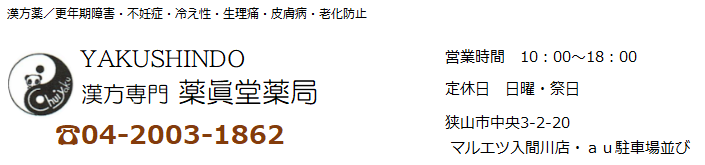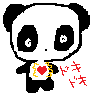 唐突ですが、数分間息が吸えないと死んでしまうのは何故でしょう?この事は人の身体にとって空気(酸素)がいかに重用かがわかります。これを運んでいるのが血脈です。梗塞をおこした部分の周囲は酸素が受け取ることが出来ずに壊死してしまいます。
唐突ですが、数分間息が吸えないと死んでしまうのは何故でしょう?この事は人の身体にとって空気(酸素)がいかに重用かがわかります。これを運んでいるのが血脈です。梗塞をおこした部分の周囲は酸素が受け取ることが出来ずに壊死してしまいます。
それが心臓や脳など身体の中枢でおきると大変な事になります。
血の巡りは全身の問題です。漢方では“瘀血”のうちに入ります。瘀血を生じ易い疾患としては糖尿病・脂質代謝異常・高尿酸血症・高血圧など考えられます。しかし、そればかりではありません。血が巡ると言う事はどう言う事なのかを考えてみたいと思います。
心臓は血液を運ぶポンプの役割をしています。中医学では『心は血脈を主る』いい、全身の血の巡りの中心です。心のエネルギーは心気といい、心気が充足していれば身体全体が栄養されるわけです。もし疲労でエネルギー不足の状態で心気が不足すれば、血脈の流れも悪くなります。これは気虚により瘀血が生じるという状態です。この時まだ血の巡りが悪い血滞の状態で瘀血に発展していなければ、補気薬を使います。原因は疲労から気虚になった状態ですからまず気を補います。しかし疲労が重なって過労になると、もうすでに瘀血の状態があると考える方が良いと思います。悪くすると循環器に影響が及んで過労死になる場合も考えられます。そのときは補気薬+活血化瘀薬を使い身体を守る事をします。これは未病先防です。
気が不足すると巡りが悪くなると言う事がわかりましたが、血が不足するとどうでしょう?臓腑や身体の各器官の滋養する血が足りないわけですから、当然隅々まで行き渡らない事になります。また『血は気の母』『気は血の帥』というように血を素にして気が作られ、気と言うエネルギーがあって血もつくられるという事がいえるので、気も不足傾向になります。
足りない為に流れないと言う事になりますし、各細胞や臓腑も充分養われないと言う事です。という事は心血も不足してくると、心も養われないため、動悸・不眠・不安などの症状も現れます。血の不足によって、血の流れが停滞する時は補血薬で血を補えば改善されます。しかし、長引いて瘀血になった時は補血薬+活血化瘀薬で改善します。
血が巡る為に気(エネルギー)がいるわけですが、気虚(エネルギー不足)については書きましたが、気滞(エネルギーの滞り)という事もあります。ストレスにより肝のエネルギーのコントロールをする働き(疏泄機能)が失調すると気の停滞が起きます。ちょうど信号機が故障して、それぞれの統制がとれずに渋滞してしまうのと同じ状態です。
気滞は瘀血に必ず発展するので『気滞血瘀』という言葉があるくらいです。血管運動にかかわる筋肉は平滑筋で自律神経に支配されています。自分の意志で動かせるわけではありません。ですから、ストレスの影響をうけやすい事がわかります。
もう一つ、血液自体が不用物でドロドロしやすいという事があります。血糖値が高い、コレステロールや中性脂肪が高い、尿酸値が高いなどは汚れた川の流れが悪くなるのと同じです。特に曲がり角や太い流れから細い流れに行く所は不用物が溜まり易いのは川の流れを想像しても明らかです。その証拠に糖尿病の合併症は目や腎臓や抹消など微小循環の部分でおきています。中医学(漢方)では瘀血になりますが、瘀血は万病の元というのは頷けます。
もう一つ潤い不足(陰虚)で血の巡りが悪くなると言う事があります。この陰虚というのは陰陽の陰が不足していることですが、解りにくいと思います。陰が不足するわけですから、バランス的に身体は陽に傾きやすくなります。これによってでる熱エネルギーは虚の熱(虚熱)です。虚熱によって身体は乾燥しやすくなります。
また人において陰は形で物質面・陽は気でエネルギー面です。ですから形態的な部分が不足しているのですから、血の水分を含めた全体量も不足するばかりでなく、血管の柔軟性もなくなってきている状態です。こういった状態で血の巡りが悪い場合は滋陰・生津という方法が中心になります。例えば、麦味参顆粒や炙甘草湯や天王補心丹などがそれにあたります。瘀血があれば活血化瘀薬を加えます。沙棘はもともとはチベット医学で使われてたものだそうですが「潤おす」「巡らす」の両方の働きがあります。
糖尿病も脂質代謝異常も高血圧も最終的には循環器や微小循環に影響するから大変なわけで、『血の巡り』の病気といって過言でないくらいです。例えば血糖値が高いということは・・・合併症が心配です。この合併症のほとんどは高血糖状態つづくことで循環障害をおこす為におきます。糖尿病網膜症は網膜の毛細血管が障害をうけ、出血がおきます。
これが進行し血流が滞り、網膜の細胞の酸素不足を補うかのように(弱くて破れ易い)新生血管ができます。これの出血によって目の見えにおおきな障害をもたらす事もありますし、新生血管が緑内障をひきおこす事もあります。また、糖尿病性腎症も腎臓の糸球体という毛細血管の集まった所の循環障害が起き、少しづつ腎不全へとすすんでいきます。
これだけ見ても、身体中を『血が巡っている』ということの重要性がわかります。血の巡りの悪さは病気という形で見えないうちに進行する事も多いものです。私達は年齢と伴に少し弱い部分がでてきます。それを補いながら巡らしてあげる事は健康の源です。
2006年3月ブログ 暮らしの中の中医学より
新潟大医学部の阿保先生が自律神経が白血球の働きを支配しているということを『免疫革命』という本の中で書いておられます。自律神経というのは『肝の疏泄を主る』という働きと近いものがあります。この疏泄を主るという働きを中医学の本で見てみると4つの機能に分類してあります。
1、気機の調節
2、脾胃の運化機能の促進
3、胆汁の分泌、排泄機能
4、情志の調節
1,気機の調節とはどういう事でしょう。五臓・経絡・その他身体の器官の活動に関係している気の動きを調節しているということです。この働きが失調すると気の流れが悪くなったり鬱滞し、肝の経絡部分に脹るような痛みや不快感を感じたりします。また、肝は剛臓で『昇を主る』のでこの働きがオーバーヒートすると『肝気上逆』となってイライラして怒る・頭痛・眩暈、さらにひどいと失神することもあります。
脾胃の運化機能ってなに?
私たちは食べたり飲んだりする事で栄養や水分を吸収し、身体の原動力にしています。この栄養や水分の吸収や代謝を運化といいます。“脾は運化を主る”といいますが、この働きを円滑に行う為に肝の疏泄機能がかかわっています。肝の疏泄が失調すると脾の昇清・胃の降濁(身体に必要なものを体に昇らせ、不必要なものを降ろしていくという働き)もうまくいかなくなります。その時は肝気が脾や胃を犯したと考え、肝を治療することで脾胃の症状を治します。
肝の疏泄機能は胆汁の分泌・排泄にかかわっているので、肝気が鬱すると口が苦い、消化不良などの症状があらわれます。情志の調節も肝の疏泄機能とかかわっています。肝の疏泄機能が正常なら、気機は円滑に機能し、気血は調和するのでのびやかで明るくなります。疏泄が失調すると肝気がオーバーヒートしてイライラ怒りっぽくなったり、肝気が鬱結してうつ状態になったりします。心と身体はつながりは双方向。気持ちのスイッチの入れ替えで疏泄機能が改善すると体の機能も動き始めます。
『肝の疏泄』は身体のコントロールセンターのようです。肝は『将軍』です。調子を崩すと色々な所に横槍をいれます。
胃痛に胃の薬?
動悸に心の薬?
咳に肺の薬?
排尿異常に腎の薬?
その症状は『肝』からきていませんか?肝からきているなら治法は『疏肝』『理気』『瀉肝』『柔肝』などですが『補血』『滋陰』も必要だったり複雑な場合多いです。
肝の疏泄が失調していませんか?肝気が鬱結してます。肝鬱化火でイライラが強くなってます。肝の腑の胆が弱って不安感がでています。肝が失調している人は多そうですね。
2006年3月ブログ暮らしの中の中医学より
漢方の症ってなに?あの漢方もこの漢方も更年期障害ってかいてあるけど?漢方は漢方の見方に基づいた薬効があります。逍遥丸の効能・効果を見てみると“冷え性、虚弱体質、月経不順、月経困難、更年期障害、血の道症”となっています。方剤学に書かれた遥散散の効能は“疏肝解鬱・健脾和営”です。簡単にいえば“肝の疏泄の働きを改善して気の鬱滞を解き、脾を健やかにして栄養する営みを調和する”という効能をもった漢方薬ということです。この薬効を理解し運用するには五臓の『肝』や『脾』の働きを理解してなければなりません。
昨日の講演はとても有意義でした。中国から来たトン先生は演歌歌手の細川隆似でなかなかの男前。先生は中国中医科学院・広安門病院(日本の東大病院にひってきするとか)の副院長で糖尿病の研究をしてこられた方です。糖尿病の合併症予防に活血通絡排毒がいかに重要かが理解できました。
では逍遥散はどんな状態の時使う漢方薬なんでしょう?『肝鬱血虚、脾失健運』となっています。肝の血が不足し、肝の疏泄の働きも失調してるため鬱滞している。脾も弱って、正常な運化ができないと言うです。つまり血虚タイプでストレスに弱く、胃腸の働きが弱かったり、水分の代謝がわるかったりするタイプの人は合ってるということになります。この状態であれば老若男女誰に使ってもいいと言う事です。効能書きをみると男性には「女性の漢方薬じゃないの」と言われそうですね。
鬱滞するものは熱をもちやすい性質があります。逍遥丸をつかうような症状が化熱するとイライラがつよい・おこりっぽい・顔が紅潮する・口が乾くなど熱の症状がでてきます。肝鬱化火といいます。この時は逍遥散に火を消すものをいれます。牡丹皮と山梔子がそれにあたります。逍遥散+牡丹皮+山梔子=加味逍遙散です。体質が陽性の人は化熱しやすいので加味逍遙散があってますが、化熱もないのに冷やすのはよくないですね。
脾はとても重要です。東西南北の方位の中央にあり、飲食物から気血津液をつくり五臓を養っています。肝鬱とは肝の疏泄という身体の気機を調整する働きが悪いということで、気が鬱滞してスムーズに流れない。血は気というエネルギーによって流れているので、その気が鬱滞すれば血もまたスムーズに流れない。状態が長引けば瘀血になります。それを気滞血瘀といます。
肝鬱血虚・脾失健運の症状に「痛む・しこる・黒ずむ」の瘀血の症状が加わる事もしばしばです。そうなったら逍遥散+活血化お薬という処方構成にします。もし脾の運が失調した為、「痰」の存在が明らかなら(+化痰薬)とします。身体に合わせて使います。
**頂いた薔薇の花がやっとひらいて喜んだら、蕾が2つ落ちてしまいました。見ると花の首の所が細くなっていたので水や栄養がいかなくなってしまった(瘀血)みたいです。お水たっぷりが好きなタイプなんだと思い受け皿に残るくらいたっぷりあげました。あと2つの蕾は絶対咲かせるぞー! **
漢方薬は身体を調整するものなもで、崩れたバランスの調整になるように使わなくては意味がありません。その為、気虚・血虚・陰虚・瘀血…など中医学の見方が大事なのです。例えば不眠に効く漢方薬と一口にいっても酸棗仁湯・天王補心丹・帰脾錠・温胆湯・牛黄清心丸など、それぞれ方意(方剤が意味する所)が違います。
「眠れる漢方薬をください。」
「それにはこれがよく効きます」
こうだったらいいのですが、そう言う具合にはいかないのです。漢方薬は病名とのつながりより、体質や現れている症状とのつながりを重視していい効果がえられます。『同病異治、異病同治』…同じ病気なのに治療方法が異なっているし、異なった病気なのに治療方法が同じと言う意味 この言葉に漢方薬をつかう意味が込められています。
寒か熱か?
湿気か燥か?
虚か実か?
陰か陽か?
表か裏か?
気血津液は?
五臓は?????
これらのアンバランスを正す事が自然治癒力アップにつながります。1つの植物の持つ薬効だけをたよりに使っていって、その結果、寒を寒し、燥を燥しというふうにアンバランスを助長してしまう事のないように気をつけましょう。
2006年3月ブログ暮らしの中の中医学より
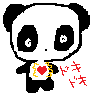 唐突ですが、数分間息が吸えないと死んでしまうのは何故でしょう?この事は人の身体にとって空気(酸素)がいかに重用かがわかります。これを運んでいるのが血脈です。梗塞をおこした部分の周囲は酸素が受け取ることが出来ずに壊死してしまいます。
唐突ですが、数分間息が吸えないと死んでしまうのは何故でしょう?この事は人の身体にとって空気(酸素)がいかに重用かがわかります。これを運んでいるのが血脈です。梗塞をおこした部分の周囲は酸素が受け取ることが出来ずに壊死してしまいます。